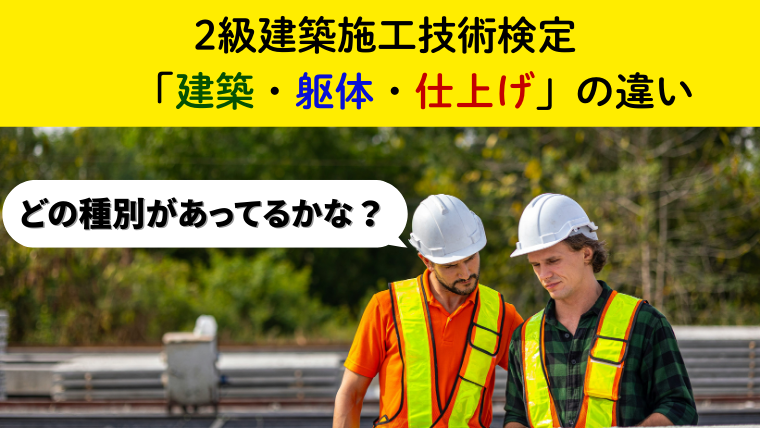建築施工管理技術検定二次検定の記述問題変更点

令和6年度(2024年度)に建築施工管理技術検定の受験資格が改正されました。
これに伴い、令和6年以降の建築施工管理技術検定問題の見直しも実施され、令和6年度の二次検定における問題1では以前と異なる様式の設問となりました。
今回は問題1について令和6年度以降と令和5年まででどのように問題の内容が変わったかのか、解答例と一緒にみていきましょう。
この記事には広告を含みます。
各問題の概要
まず、二次検定がどのような設問なのか整理します。
二次検定は一次検定の選択問題と異なり、自分で解答を記述する問題が出題されます。
ただ、すべての問題が記述式というわけではありません。
中にはマークシート式もあります。
設問は問題1~問題5までです。
問題1:施工経験記述(能力)-記述式
問題2・問題3:建築分野別記述(能力)ー記述式
問題4・問題5:建築分野別記述(知識)ーマークシート式

問題4と問題5は選択問題です
問題1は「施工経験記述」。
建築工事における品質管理、施工計画、工程管理に関する記述問題です。
問題2は「建築用語」。
建築工事に関する用語の説明と施工上の留意点を記述させる問題です。
問題3は「工程表」。
提示された工事の概要に対して工程表や出来高表を読み解く問題です。
問題4は「法規」。
建設業法や建築基準法施行令、労働安全衛生法等の法令関係の問題です。
問題5は「施工管理」。
受検種別(建築・躯体・仕上げ)ごとに異なる専門的な問題が出題されます。
個人的な感想ですが各問題の難易度はこんな感じです。
★の数だけ難しくなるよ!
問題1(令和5年まで):
問題1(令和6年から):
問題2:
問題3:
問題4:
問題5:
問題1は令和6年からやっぱり難しくなったんじゃないかな、と思います。
かくいう私も令和6年度が二次検定初挑戦でしたが、過去の出題の仕方と比較して難しく感じました。
どの設問も過去問で対応可能ですが、
問題2は記述で用語の説明を書かせるため難しく、
問題3は要点を掴みやすく、
問題4と問題5は暗記ですが選択式なので多少は楽です。
また配点はおおよそ、
問題1:40点
問題2:20点
問題3:12点
問題4:12点
問題5:16点
合計100点
となっています。
令和5年までの記述問題1
令和5年(2023年)までの建築施工管理技術検定の問題1は下記の特徴があります。
- 解答者自身が経験した建築工事をもとに解答する
- ❶のため工事概要の設定を自分で行う
- かなり専門的な工事内容でも自分の経験を基に解答できる
工事概要というのは、例えば令和5年度では下記になります。
- 工事名
- 工事場所
- 工事内容
- 工期等
- あなたの立場
- あなたの業務内容
上記の項目を自分で決めて問題に解答します。
問題1のなかに設問が2つあり、1つ目の設問(問題1-1とします)が自分で設定した工事概要について答えさせる問題です。
2つ目の設問(問題1-2とします)は工事概要に関わらない一般的な問題を記述させる設問です。
前述した問題1(記述)の特徴は問題1-1についての特徴です。
この2つ目の設問も厄介なのですが、問題1-2に関しては特に令和6年以降でもその出題形式に変更が無いので今回は問題1-1のみに絞って書いていきます。
問題1-1(令和5年度)
令和5年度を例にすると問題1-1は
以下の項目Aからテーマを選び施工計画を立てる際に、工事を遅延させないためにどのようなことを行ったのか項目Bの①から③について事例を3つ記述させる設問でした。
項目A
a.材料(本工事材料, 仮説材料)
b.工事用機械・器具・設備
c.作業員(交通誘導警備員は除く)
項目B
①工種名又は作業名等
②遅延させるかも知れないと考えた当時の状況とそれが遅延につながる理由
③②による遅延を防ぐために実際に行った対策
令和5年度 2級建築施工管理技術検定 二次検定問題
例えば建具工事において項目Aのc.作業員をテーマに決めたら、以下のように解答します。
①建具工事
②現場が入り組んでいる状況で、部材同士の接触や建物への接触により製品及び建物を傷つけてしまうことで補修に時間を取られ、工事の遅延につながると考えたため。
③事前に搬入経路を確認し、作業員に周知して、搬入時の人員を増員し、長尺な部材の搬入は2人以上の体制で搬入する計画を立てた。
工事種別の部分が、解答者の経験により様々ですが
例の②、③の解答の仕方は割と汎用性(複数種類の工事種別で共通)のある解答かもしれませんね!
問題としては施工計画の部分が品質管理や工程管理に変わったり、
項目Aや項目Bの内容が変わりますが
工事概要を自分で設定できる以上、
案外自分の経験則だけでなんとかなっちゃいます。
もちろん事前に何を書くか整理する必要はありますけどね。
自分の実務経験が
とび職だろうが、石工事やタイル工事だろうが
自分の土俵で解答できるのが令和5年までの問題1でした。
令和6年以降の記述問題1
令和6年(2024年)以降の問題1は以下の特徴があります。
- 設問にあらかじめ示された工事概要に対して解答する
- 2級施工管理技術検定では複数提示された工事概要のうち1つを選択して解答する
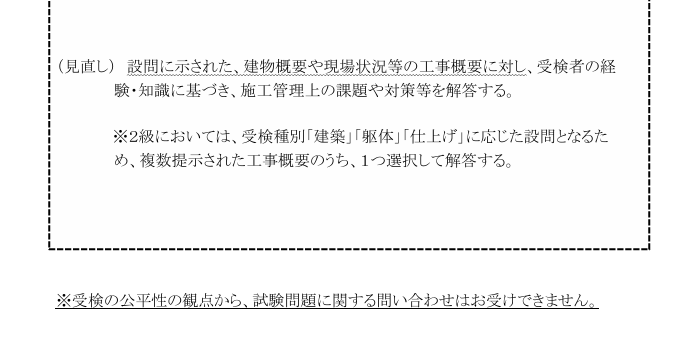
なんといっても建物概要や現場状況を自分で設定できなくなった点が大きな見直しといえるでしょう。
これまで自分の専門分野で勝負できた問題が
今後は自分が経験した工事が出題されるとは限らなくなってしまった以上、
問題に対する対応力を身につけるため
これまで経験してこなかった工事も勉強する必要があります。
令和6年の問題1も設問は2つあり、1つ目(問題1-1とします)は工事概要をみて解答させる問題。
2つ目(問題2-2とします)は提示された工事概要に関わらない「品質低下」と「公衆災害」の防止についての問題でした。
問題1-1(令和6年度)
令和6年度問題1-1はまず工事概要「新築」、「解体」、「改修」のなかからいずれか1つ選びます。
選んだ工事概要において、a~cそれぞれについて①~③を具体的に記述させる設問でした。
[施工計画時の検討事項]
a.施工又は作業の方法
b.資材の取り扱い方法(搬出入、揚げ降ろし、保管、仮置き等)
c.施工中又は施工後の養生の方法(ただし、労働者の安全に関する養生は除く)
①工種名又は作業名等
②検討すべき作業内容とその作業における懸念事項
③②の懸念事項に対する対策
令和6年度 2級建築施工管理技術検定 二次検定問題
a~cそれぞれに解答していくので、3つ解答することになります。
解答数は令和5年までと変わりません。
ここで工事概要「新築」を選んだ場合の解答例を1つ挙げようと思います。
「新築」の工事内容は下記でした。
工事内容:鉄筋コンクリート構造 共同住宅新築工事
工期:2024年1月~2024年12月
この記事では載せませんが実際の問題用紙には上記の工事に関する概要が提示されます。
施工計画時の検討事項: a 施工又は作業の方法
①鉄筋コンクリート躯体の配筋作業
②躯体の配筋作業において、台風や大雨による作業不能日の発生により工期が遅れる懸念がある。
③工場であらかじめ鉄筋を組んでから現場に搬送するユニット鉄筋工法を採用することで現場作業を短縮することで余裕のある施工計画とする。
今回、工事の内容が鉄筋コンクリート造というのもありますが、
上記の解答例は鉄骨造でも基礎の配筋に対しても使えるかもしれませんね!
まとめ
やはり検定が始まらないとどのような工事概要かわからない、というのは大きな変更点です。
もしあらかじめ勉強していた内容が鉄筋コンクリート造に偏っていた場合、
検定が鉄骨造の工事概要に対しては解答が難しくなるケースもあります。
対策としては以下が考えられます。
- 過去問で幅広い職種について勉強する
- そのような構造種別に対しても汎用的な解答を用意する
- とにかく空欄をつくらないよう対策する
自分の仕事の経験だけで解答することが難しくなったので、
過去問等で幅広い分野の職種の知識を深めていく必要があります。
ただ、大抵の工事で共通する工事もあります。
基礎工事や内装工事などはいくつか勉強しておくと
検定当日1問ぐらいは解答できるのではないでしょうか。
また、空欄を絶対につくらないことも大切です。
解答が全く思い浮かばなくても、部分点がもらえるかもしれません。
せっかく一次検定に合格したのですから、
最後までやり切って終わりましょう!