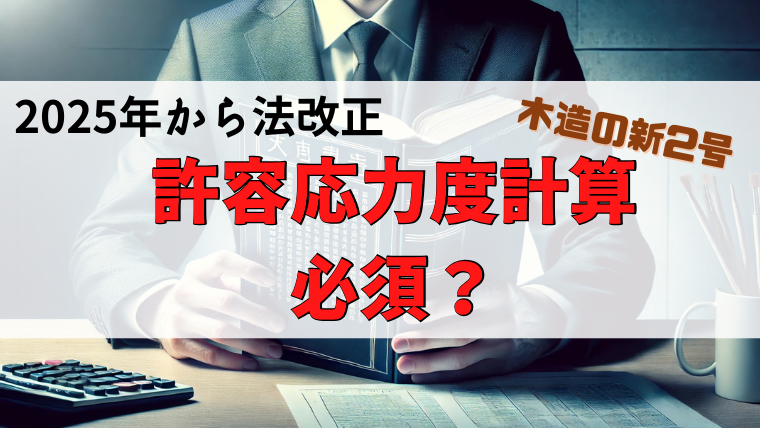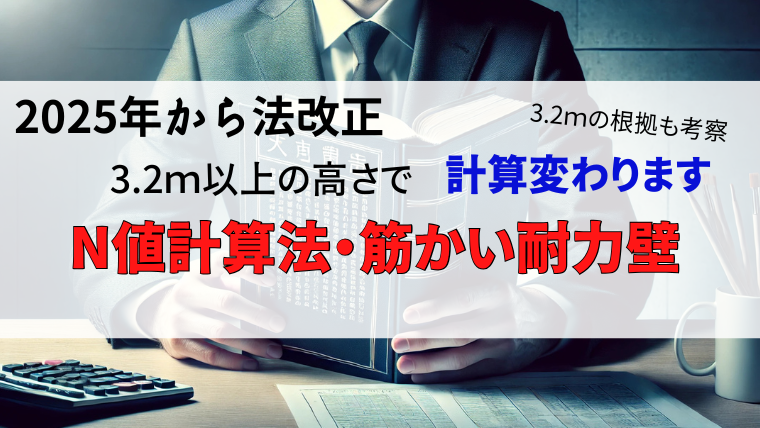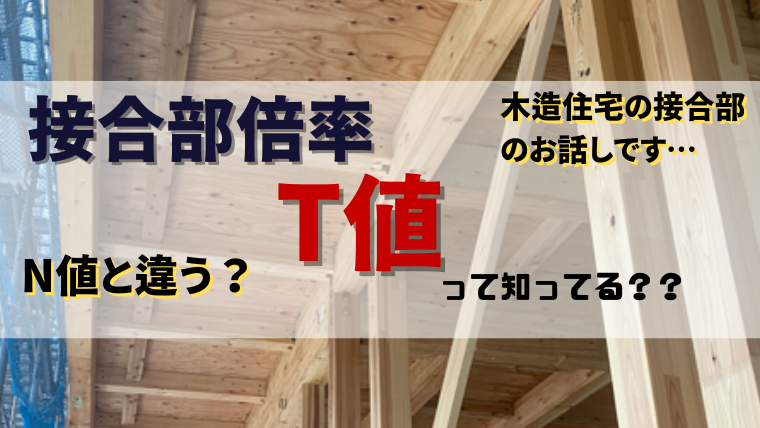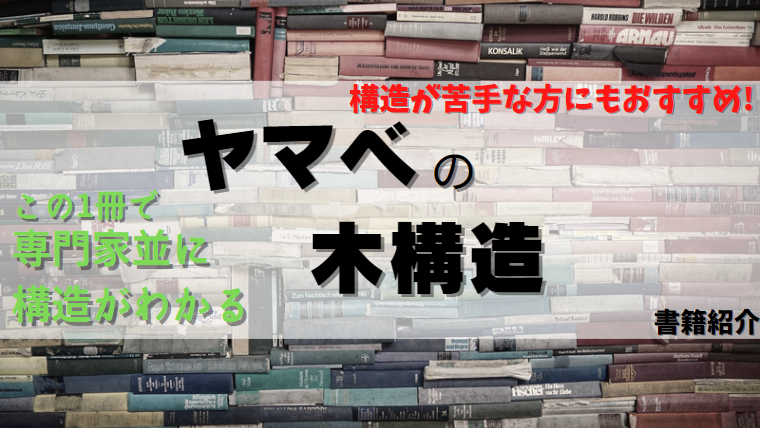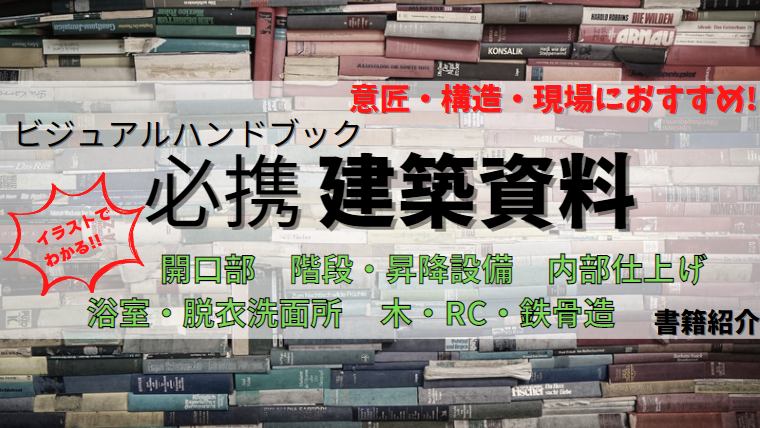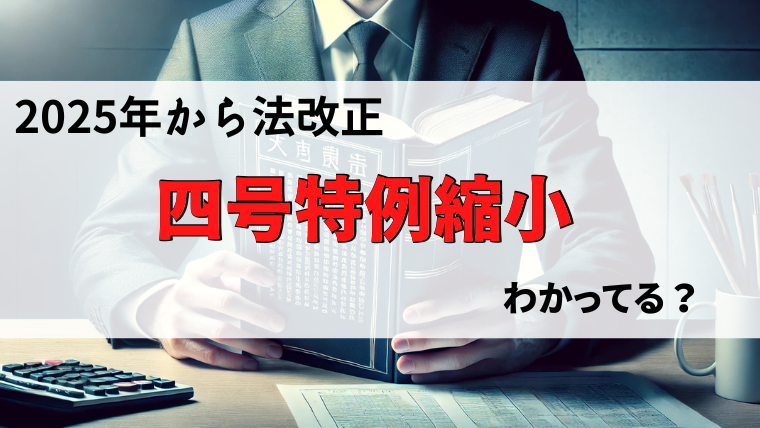RC造の断面詳細図も即解決!おさまり詳細図集 配筋要領編
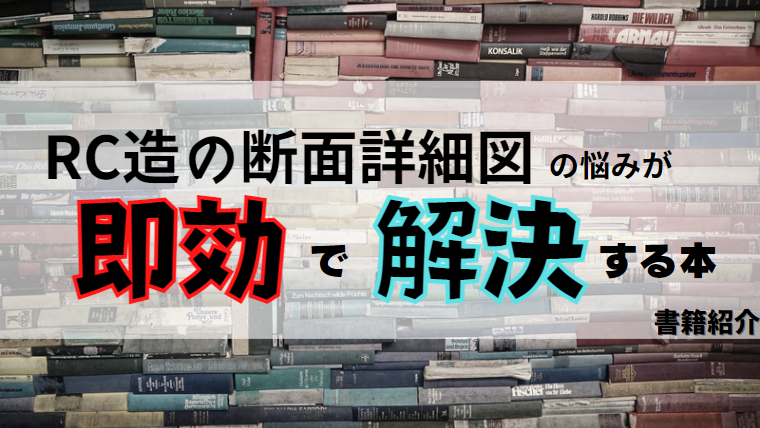
皆さんはRC造の構造設計もしくは平面詳細図や断面詳細図、施工図を考えるときに配筋の仕方で悩んだことはありませんか?

定着長とかの規定値はわかるけど階段とか基礎の配筋をどうするのかイメージしづらいな…
RC造の配筋って鉄筋のかぶり厚さとか定着長だけ知っていても設計や作図できるものじゃないですよね。
部材の一般部はわかるけど、高低差のある梁が1つの柱に接合したり、階段と壁の納まりだったり、貫通孔回りの補強筋など経験の浅い人からしたらどれも悩ましい問題です。
今回は僕がRC造の構造設計やCADオペ(CADオペレーター:CADで図面を作成する専門の人)に詳細図をお願いする際にいつも参考にしていたおさまり詳細図集 配筋要領編を紹介します!
本の構成
おさまり詳細図集 配筋要領編の構成は以下のようになっています(目次より抜粋)。
- 共通事項
- 基礎の配筋
- 柱の配筋
- はりの配筋
- 床スラブの配筋
- 階段の配筋
- 壁の配筋
- 各部開口回りの補強配筋
- 増築予定部の主筋のおさめ方
- 壁式構造の配筋要領
- 補強コンクリートブロック造の配筋
- 付録
見てわかる通りRC造における配筋のほとんどをこの1冊で参考にすることができます。
また、RC造の部材別に配筋の詳細図がほぼすべてのページに使われています。
ちなみに共通事項というのは鉄筋の規格や種類、定着や継手長さ等のあまり部位に関係なく一般的な内容が書かれています。
最後の付録は巻末資料のことで、特に本書と切り離せるとかではありません。
付録には主に施工時の話が書かれています。
特に購入してよかったと思える点
僕の感想といいますか、この本をおすすめできるポイントも兼ねて僕自身が実際に配筋について参考にして悩みを解決できた部分をお伝えしたいと思います。
まずは配筋で悩んでいた部分、わからなかった部分です。
- 杭基礎のフーチングの配筋
- 地中梁とべた基礎のハンチ部分に対する配筋
- 柱が上下階で異なる断面サイズの場合の配筋
- 梁天端が柱の左右で異なる場合の配筋
- 平面的に梁が柱に斜めに取り合う場合の配筋
- 床に段差がある場合の配筋
- 階段の段差部の配筋
- 階段と階段を受ける部材の納まり
- 壁と壁の取り合いにおける配筋
- パラペットの雨押えの配筋
- 梁やスラブの貫通孔回りの配筋
- ひさしの配筋
次にこの悩みに対してどのように解決できたか、参考になったか、というのが以下になります。
もちろん上記だけでなく、新卒だったころは一般的な部分の配筋も大変参考になりました。
まとめ
先ほどリストアップしたのは、RC造の一般的な部分というよりは、建物全体のほんの一部分や端部の納まりなど、ネットで調べようとすると苦労しそうな部分ばかりです。
構造設計者は意匠側からの様々な要望に応えるため、こういった詳細図でイメージしやすい参考書で対応力を磨きたいところですよね!
実際に詳細図を作図するCADオペの方も、この本を持っていればきっと心強いはず!
また、本書には各章のところどころに施工上の注意点も書かれていました。
配筋の要領だけでなく、コンクリート工事やRC造における「普通」や「一般」を勉強できるので是非購入してみてください!